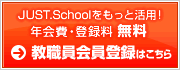中学・高校の実践事例
学校生活を見つめる子どもたちの目 パソコンの豊富な機能で個性をプラス
〜写真を使った学校紹介。『ー太郎ジャンプ』でオリジナルの作品づくり〜
神奈川県・横須賀市立池上中学校
子どもたちに学んで欲しいのは“生きる力”としての情報モラル

池上中学校では、今回のように教科のなかでパソコンを使う以外に、行事に合わせて新聞を作るなどの活動に取り組んでいる。
「ただ単にパソコンを使った授業をするのではなく、情報を活用する能力の育成を目指しています。試行錯誤しながらですけどね(笑)」と、授業を担当した栗原先生。
また、今後、情報教育を推進していくなかで子どもたちに身につけて欲しいこととして、情報モラルを一番に挙げる。
「一般家庭のパソコン普及率が上がる一方で、子どもたちの親の世代は情報モラルについての知識が少ないという問題があります。その部分を学校でフォローするべき。大きく言ってしまえば“生きる力”としての情報の能力を身につけるのが目標です」
具体的には、市の教育委員会が作っている情報モラルに関するソフトを使って、メールのやり取りやショッピング、著作権などを学習させる。
特に、今年は著作権に関して深く学習する方針で、子どもたちに、著作権に関するビデオを見せたり、ホームページのクイズに答えさせるなどして、興味を持たせていく予定だ。また、県の教育委員会が作成したチャットやショッピングなどの疑似体験ができる 「モラルCD」も活用するとのこと。
子どもたちを取り巻くさまさまな情報環境のなかで、危険に巻き込まれることがないよう、道しるべを立ててあげることが教育者の使命だと、栗原先生は考えている。
パソコン環境を統一し、情報教育の年間カリキュラムを提案する、横須賀市の取り組み
池上中学校がある横須賀市は、情報教育に関して独自の活動を進めている地域で、市立の学校のパソコン設備やインターネット環境を統一しているのが特徴だ。
「今までは、学校や先生によってパソコン導入のレベルが違っていました。ある程度操作ができる子どもと触ったことがない子どもが一緒に授業を受けるという状況が、大きな悩みだったんです」と語るのは横須賀市教育研究所の小谷孝夫氏。これは、どの地域でも共通の課題だ。
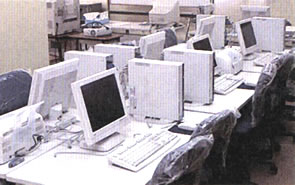
平成11年9月に、全ての市立中学校にパソコン室を導入、翌12年には学校インターネットに接続した。さらに13年度には小学校にもパソコン室を設置、市立の全学校が光ケーブルでつながった。
また、機種やOS、ソフトなども統一している。子どもたちは同じ環境で情報教育を受けることができ、先生にとっては市内のどの学校に転勤になっても、常に同じ環境でパソコンを使うことができるというメリットがある。
さらに、指導内容についても平均化を図る取り組みに着手。横須賀市情報教育研究会では、小学校を対象に情報活用能力育成の年間カリキュラムの試案を作成した。試案では1学年ごとに抑えておきたい基本動作や、学ばせたい情報モラルを挙げ、各教科における活用目標を示している。

例えば、国語においては 「ひらめきライターでの文書作成」など、試案といっても実に具体的だ。さらに、市内の小学校の研究資料をベースに作成された学年別の年間指導計画では、1年生7月の 「電源を入れて絵を描いてみよう」から、6年生1月の 「卒業記念CD-ROMを作ろう」まで、細かい例が挙げられている。
「ただ、これはあくまでも参考です。このカリキュラムをもとに、それぞれの学校や先生で時間数を増減し、創意工夫をしてもらうように提案しています」 と小谷氏。 「小学校では基本を学び、中学校ではさらに深い部分の学習を目指したいと考えています。小中一貫したカリキュラムだと、子どもたちの伸び方も違うし、先生たちも指導しやすいのでないでしょうか」
パソコンやインターネットを使った学習活動をいかに素晴らしいものにしていくか。また、その環境を先生たちはどう活かすのかが、最大のポイントだ。全国的にも珍しい市全体での取り組みの今後の動きに注目したい。
*写真 左から 栗原先生、横須賀市教育研究所の小谷孝夫氏、池上小学校の深本彰先生。
昭和22年開校。あいさつ、時間、ルール、集中力の、4つの生活基本をベースに、自立性のある生徒の育成を目標にしている。平成13年には野球部が県大会で優勝するなど、部活動も盛ん。校長先生が自ら制作しているという学校ホームページも充実している。生徒数413名。