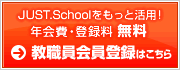中学・高校の実践事例
メディアリテラシーでモラルを 人権教育で国際感覚を学ぶ
〜国際理解と情報発信する力を養う教育〜
大阪府・東大阪市立柏田中学校
花園ラグビー場で有名な東大阪市の西南部、大阪市との境に位置する柏田中学校。校区には、中小企業の工場が多く世界に誇る技術をもったものもある。また在日韓国・朝鮮の方も多く住んでいることもあり、子どもたちに“他文化共生”の視点での豊かな“人権教育”“国際理解教育”と自らの未来を切り開く“進路”指導の充実をめざして、地域とともに歩き出している中学校である。
メディアリテラシー授業で情報を扱うモラルを指導
毎週1時間は“メディアリテラシー”の時間を設け、情報教育の基礎を培っている柏田中学校。メディアリテラシー授業を担当するのは、技術科の平川保一先生だ。
「1年生には、1学期から情報モラルについて教えてきました。主にタイピングソフトなどを使ったコンピュータの操作の基礎と著作権・モラルなどです」
入学して初めてパソコンに触れる生徒も多く、生徒もとまどいがち。小学生なら、ものめずらしさで飛びついてくるところだが、中学生ともなると構えてしまう、と平川先生は感じている。
「思春期の難しさでしょうか、パソコンに慣れていない子は構えてしまうのでしょう。何かひとつとっかかりがあるとできるようになるのですけど」

そんな平川先生が1年生の生徒に出した技術科の夏休みの宿題は、自由工作。生徒がそれぞれ思い思いに木材を使って、何かを作製してくるというものだった。
「これを元に発表資料を作ります。自分で苦労して作ったものを発表し合う中で、他人を尊重する意識を身につけて欲しいのです」
まずは『はっぴょう名人Teen's』を使って、先生が見本を作る。これを参考に自分の製作物のプレゼンテーションを作るのが今回の課題だ。 「体育祭もありましたし、次に文化祭も控えていますから、なかなか進まないんですけど・・・」といいながらも、ひとつひとつの操作を丁寧に生徒に伝えていく。
先生が説明する際は、生徒用パソコン4台の真ん中にあるモニターが、先生用パソコンの操作を映し出し、生徒が確認しながら作業を進めていく。プロジェクターを使って、教壇の後ろのホワイトボードに画面を映し出して説明する場合もある。
「明るい室内でも十分に画面を映すことができ、生徒の顔を見ながら説明できるところがいいですね」
今後はもっとプロジェクターも活用したいと考えているようだ。
『はっぴょう名人Teen's』を使って 「私のもの作りカード」を作ろう!
まずは、デジタルカメラを使って製作物の撮影。 「どういう構図がいいかな?」初めてのデジタルカメラ体験だ。生徒が撮影した画像は、各自のフロッピーに保存し、いよいよプレゼンテーション用にまとめていく。
取材当日は、4ページ目の 「製作作品」に作品の外観写真を挿入する作業を行っていた。[絵や写真]アイコンからフロッピーに保存された画像を挿入する。
学校行事もあり、1年生が『はっぴょう名人Teen's』を使うのは、これで2回目。作業をはじめる前に、平川先生は先生用パソコンを操作しながら説明していく。
「授業の中でたくさんのことを言っても生徒はついてきません。できるだけひとつずつ段階を追って、ポイントを絞って説明しています。わかってしまえば、子どもの方が早いんですよ」

写真の挿入では[グリッドの表示]を使った位置の合わせ方を指導していた。生徒は2つの画像の位置やバランスをグリッド線に合わせていく。生徒たちがつまづいているようであれば、指導補助員の星川信明先生がすかさず助けに入る。
なかには、作品をまだ完成させていない生徒もいて、手持ちぶさたの様子。そんなとき、星川先生が素材集を渡し 「これで好きな画像を入れる練習をしてごらん」と声をかける。
「パソコンを使った授業だと子どもの進度に差があるので2人で教えた方が対応が早い。その分、内容に助言できるのできめ細かく指導できます」
写真の挿入が終わったら、今度は 「製作作品」の部分を自分の作品のタイトルに変更。右下の部分には“工夫した点・特に見て欲しいところ”を書き込んでいく。
生徒の作品タイトルは 「小さなお家」 「ほんたてクン」 「ぬいぐるみイス」 「マンガ入れ」 「僕の本棚」 「CD入れ」とさまざま。 「ローマ字で打つの?」 「この前、どうやったっけ?」キーボードの操作にとまどいながらも、タイトルの文字を自分の好きな色に変えている生徒もいる。 「色を変えている人がいるな。素晴らしいぞ!」平川先生は、入力した文字に、色見本から好きな色を選んで色をつけている生徒に声をかける。
メディアリテラシーの習得で発表する力を養う
4ページ目の作業が終わったところで授業の終わりを告げるチャイムが鳴った。
「できたものをフロッピーに保存するぞ」
平川先生の声かけで、生徒たちは[保存]のアイコンを押し、フロッピーを先生の机に集めていく。
「生徒は、ほかの授業よりもパソコンを使った授業は好きですよ。いつも時間より早く集まってきています」
平川先生は、パソコンを扱う生徒たちに対して 「1台のコンピュータを全学年が利用するわけですから大事に使って欲しい」ということを“メディアリテラシー”授業を通して伝えている。
「メディアリテラシーの最終的な目的として、自分の意見や学習したことなど発表する能力を養うことがあげられます。『はっぴょう名人Teen's』は、発表する力を引き出すために、集大成のソフトだと思っています」
と平川先生は語る。
人権教育は学校の柱 生徒には素敵な文化の出会いを
東大阪市の中学校パソコン教育研究会会長を務める倉本静夫校長は、積極的にパソコンを使った授業を推進するかたわら“人権教育”や“開かれた学校づくり”にも力を入れてきた。
倉本校長は言う。
「校区には、在日韓国・朝鮮の方が多く住んでおられる。その子どもたちが今、この中学校へ通っています。そういう出会いの中で、次代を担う本校の子どもたちには、国際感覚あふれる差別を許さない大人に成長して欲しいと願っています。そのためにも“人権教育”は本校の大きな柱として必要なのです。これからはグローバルに、様々な文化との出会いがやってきます。世界中の人々とつながることができるコンピュータは、その有効な手だてのひとつです。子どもたちに、ぜひその力をつけ、豊かで素敵な文化とたくさん出会わせてあげたい」
“開かれた学校づくり”として、“キャリアデー”“職業体験学習”など、地域の支援を得て、同市他校に先駆けて取り組み、昨年には校区幼・小・中学校と地域が協力し、一緒に“子育て”を考える 「わくわく実行委員会」を立ち上げている。
「学校が地域とともに“人権”や“教育”のことを本気で考えていかなければならない時代がやってきています。学校は地域文化の中心的役割を担い、また情報を発信していく必要があります。子どもたちには、校区の文化や産業を誇りに思える人になって欲しい。あたたかい、本当に素晴らしい校区なのですから」
と倉本校長は語った。
東大阪市と大阪市の境にある東大阪市立柏田中学校は、国際的な視野を持って人権を尊重し、豊かな人間性を育む“人権教育”と、コンピュータの基礎知識や発表する力を養う“メディアリテラシー”、社会の一員であることを実感させながら豊かな職業観を育てる進路指導などに力を入れている。生徒数287名。