
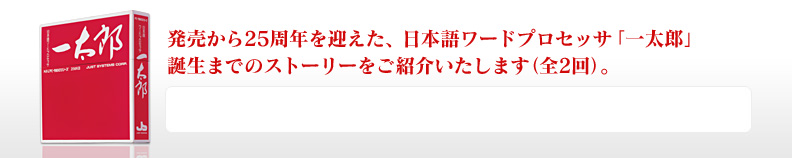
※1995年発行に発行された書籍「株式会社ジャストシステム 『一太郎』を生んだ戦略と文化」
(高橋範夫著:株式会社光栄発行)の内容を抜粋し、一部加筆・修正したものです。
(高橋範夫著:株式会社光栄発行)の内容を抜粋し、一部加筆・修正したものです。
第1回:ジャストシステム創業、日本語処理システムの開発
黎明・ジャストシステム
浮川は1979年3月31日、西芝電機を退職した。4月1日から、東芝系の「JBC」というオフコン・メーカーの販売代理店をするため、大阪で研修を受けた。2ヵ月間、無給の研修だった。エンジニアの浮川は、営業に関しては、納品伝票も知らない素人だった。10階建てのビルを前にして、「このビルに入っている会社を、今日と明日で全部回りなさい。もし1台でも売れたら給料をあげますよ」と、カタログを持たされ、ポンと背中を叩かれた。だが、商売の厳しい大阪で、1,000万円もするオフコンを、素人に売れるはずはなかった。
徳島市中常島町の初子の実家に、6月に帰ってきた。瓦屋根の実家には8畳ほどの洋風応接間があった。そこに電話1本と、幅1メートルを超えるコンピュータ1台を持ち込むと、足の踏み場もないほどになった。実家をオフィスにしたのは、少しでも経費を浮かせるためだった。
徳島に帰ることが大前提だった。会社を大きくしようとか、商売になるかなんて考えてもしょうがない。「20人くらいの会社になれればいいね」と話し合うのが、せいぜいの夢だった。

7月7日の七夕の日。みんなで夕食の食卓を囲んでいたとき、浮川が突然大きな声で宣言した。「今日を創業の日とします」
社名は「大きすぎず、小さすぎず、高すぎず、お客さんに一番満足してもらえる商品を」という意味で、「ジャストシステム」とした。玄関先に看板を掲げ、2人でスタートした。
2人の役割分担は決まっていた。浮川が営業として顧客を回り、エンジニアの初子がシステムを組むのである。初子の抜群の能力が、ジャストシステムの売りであった。この点、浮川は自信をもっていた。
商品についても、彼らの将来を占う上で、特筆すべきことがある。JBCのオフコンは、カタカナ処理がほとんどだった当時において、最新の漢字処理ができる機種だったのだ。
浮川は当時から、コンピュータで漢字を扱えないのはおかしい、将来は漢字システムを備えた機種が主流になると考えていた。「漢字が使えるコンピュータだから扱ったんです」と初子もいう。が、実際に売るのは大変だった。
まだまだ漢字処理は面倒な作業で、世間の認知もない。加えて、価格はカタカナ処理のオフコンの倍。システムと合わせて、1,000万円もした。中小企業相手に、滅多に売れるものではない。
意外なことだが、徳島は浮川はもちろん、初子にとっても馴染みのない街だった。初子は生まれは徳島だが、父親の仕事の関係で、ほとんど高松で育っていた。ジャストシステムは徳島県にほとんどコネクションがない状態でスタートした。浮川は初めての土地で、1度も経験のない営業を開始した。
1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月と、1台も売れないまま、月日がすぎた。浮川は必死だったが、ジャストシステムなぞ誰も知らないし、メーカー名もあまり知られていない。顧客側にしてみれば、大きな投資を、社員2名の会社に託すのは不安があったろう。「いいものなのはわかるが、そんなに高いものを導入したら会社が潰れる」と、よくいわれた。
数力月、注文のない鬱々とした日々が続いた。焦りと不安、もどかしさが募る毎日だった。最初の注文をもらうまでに半年かかった。
その日、「売れた、売れた」と大喜びで、家に飛んで帰った浮川を迎えたのは祖母だった。「注文取れたよ」
勢い込んで報告すると、2人に独立を勧め、いつも応援してくれた祖母がものすごく喜んでくれた。「よかったねえ」
その顔を見たとき、浮川は泣いてしまった。涙をぼろぼろ流しながら、よかった、よかったを連発した。
第1号の経営管理システムを発注してくれたのは、徳島市内の吉成種苗という農業用の種を扱う会社だった。植物や種子の名前が絡むシステムには、漢字が必要だった。
発注側の吉成社長は、浮川から「明日から女房が来ます」といわれたとき、不安になったというが、初子は半年間手弁当で通い詰め、見事なシステムをつくりあげた。細かな要望を聞き入れ、漢字も1文字ずつ入力できるようにした。その後、このシステムを手直ししようとした大手企業の技術者は、その完成度の高さに驚いたという。
初子の才能は、思い込んだら尋常でない集中力を発揮し、徹底的に突き進む性格によるところが大きい。浮川は、男性が一般的にそうであるように、あれこれ先のことを考え、周り見回して、計算ずくで動こうとする。初子は、できる範囲で、とりあえず段取りをつけて、突き進む。加えて、女性的なきめの細かさ、優しさがある。それが、すぐれたソフトウェアを開発できた要因になっている。
初子の突進力は、浮川さえも圧倒するというが、2人が互いに補完し合えば、非常に強力になるのは、容易に想像できる。
受注第1号は1,000万円足らずの仕事だったが、これをきっかけに、ジャストシステムの技術力は地元で知られるようになった。また漢字処理システムが、いっそう身近になったのも大きな収穫だった。
オフコンの事業は、この後も細々としたものだった。昼間、初子がコーディングしたものを、浮川が夜、パンチを打って仕上げる日々だった。一太郎を出すまでの6年間で売れたのは結局、1,000万円のオフコンを5セットと、パソコン数台足らずという。「売れないがために、コンピュータ化の提案書をたくさん書くなどして、この時期は経営の勉強にもなった」
オフコン上で1度だけ、ワープロをつくったことがあった。「文章をつくりたいからと頼まれて、簡単に文章をつくるような、変なワープロを作成したんですよ」
オフコンが売れないから、初子はこうした経験を積めたのかもしれない。
翌80年、徳島駅近くに事務所を構えた。14坪の賃貸オフィスだった。朝、2人で出勤し、お互いに向かい合って「おはようございます」と頭を下げて、仕事を始めた。81年には、社員6人の株式会社になった。相変わらず、注文は少なかったが、浮川には将来の展望が見えてきた。

日本語処理の将来性に対する確信は、ますます強まり、日本語処理ソフトの開発に没頭するようになった。プリンタに漢字システムを組み込んでみたり、コンピュータ上での処理を考えてみたりと、日本語のことが常に頭にあった。
当時、マイコンと呼ばれた個人ユースの8ビット型コンピュータが世間に広まり始めていた。いまでいうパソコンだが、浮川はマイコンを買ってみて、意外に高性能なのに驚いた。そして、マイコン用の汎用ソフトのことを考えるようになった。「浮川が最初にパソコンを見たとき、これからは日本語変換システムだと思ったんです。コンピュータに関わりながら、彼がずっと思ってきたのは、そういう誰でも使えるものとしてのイメージ。そして、日本人が利用する際の一番根幹のところをやりたいと考えていたんです」と初子。
浮川はそうした思想をもちながら、ビジネス面でもパッケージソフト(店頭で売られる汎用のソフトウェア)を売る方が魅力があると思った。
1,000万円もするオフコンは、そう売れるものではないし、一度売れたら、技術者はシステムが完成するまで、顧客企業にかかりっきりにならなくていけない。土、日曜日でも呼び出される。パソコン用のパッケージソフトは単価は安いが、自由につくって、たくさん売ることができる。
といっても80年当時は、パソコン用パッケージソフトの市場が生まれて間もない頃で、まともな商品はほとんどなかった。ゲームソフトを中心に、カセットテープと、コピーした手書きのマニュアルをビニール袋に詰めたようなものが、秋葉原などの量販店の片隅に置かれていた。業界と呼べるほどのものはなく、一部マニアの市場だった。
浮川はこういう時期に将来を見ていたが、実際に飛び出すまでには、もう少し時間がかかる。
徳島市中常島町の初子の実家に、6月に帰ってきた。瓦屋根の実家には8畳ほどの洋風応接間があった。そこに電話1本と、幅1メートルを超えるコンピュータ1台を持ち込むと、足の踏み場もないほどになった。実家をオフィスにしたのは、少しでも経費を浮かせるためだった。
徳島に帰ることが大前提だった。会社を大きくしようとか、商売になるかなんて考えてもしょうがない。「20人くらいの会社になれればいいね」と話し合うのが、せいぜいの夢だった。

創業社屋
7月7日の七夕の日。みんなで夕食の食卓を囲んでいたとき、浮川が突然大きな声で宣言した。「今日を創業の日とします」
社名は「大きすぎず、小さすぎず、高すぎず、お客さんに一番満足してもらえる商品を」という意味で、「ジャストシステム」とした。玄関先に看板を掲げ、2人でスタートした。
2人の役割分担は決まっていた。浮川が営業として顧客を回り、エンジニアの初子がシステムを組むのである。初子の抜群の能力が、ジャストシステムの売りであった。この点、浮川は自信をもっていた。
商品についても、彼らの将来を占う上で、特筆すべきことがある。JBCのオフコンは、カタカナ処理がほとんどだった当時において、最新の漢字処理ができる機種だったのだ。
浮川は当時から、コンピュータで漢字を扱えないのはおかしい、将来は漢字システムを備えた機種が主流になると考えていた。「漢字が使えるコンピュータだから扱ったんです」と初子もいう。が、実際に売るのは大変だった。
まだまだ漢字処理は面倒な作業で、世間の認知もない。加えて、価格はカタカナ処理のオフコンの倍。システムと合わせて、1,000万円もした。中小企業相手に、滅多に売れるものではない。
意外なことだが、徳島は浮川はもちろん、初子にとっても馴染みのない街だった。初子は生まれは徳島だが、父親の仕事の関係で、ほとんど高松で育っていた。ジャストシステムは徳島県にほとんどコネクションがない状態でスタートした。浮川は初めての土地で、1度も経験のない営業を開始した。
1ヵ月、2ヵ月、3ヵ月と、1台も売れないまま、月日がすぎた。浮川は必死だったが、ジャストシステムなぞ誰も知らないし、メーカー名もあまり知られていない。顧客側にしてみれば、大きな投資を、社員2名の会社に託すのは不安があったろう。「いいものなのはわかるが、そんなに高いものを導入したら会社が潰れる」と、よくいわれた。
数力月、注文のない鬱々とした日々が続いた。焦りと不安、もどかしさが募る毎日だった。最初の注文をもらうまでに半年かかった。
その日、「売れた、売れた」と大喜びで、家に飛んで帰った浮川を迎えたのは祖母だった。「注文取れたよ」
勢い込んで報告すると、2人に独立を勧め、いつも応援してくれた祖母がものすごく喜んでくれた。「よかったねえ」
その顔を見たとき、浮川は泣いてしまった。涙をぼろぼろ流しながら、よかった、よかったを連発した。
第1号の経営管理システムを発注してくれたのは、徳島市内の吉成種苗という農業用の種を扱う会社だった。植物や種子の名前が絡むシステムには、漢字が必要だった。
発注側の吉成社長は、浮川から「明日から女房が来ます」といわれたとき、不安になったというが、初子は半年間手弁当で通い詰め、見事なシステムをつくりあげた。細かな要望を聞き入れ、漢字も1文字ずつ入力できるようにした。その後、このシステムを手直ししようとした大手企業の技術者は、その完成度の高さに驚いたという。
初子の才能は、思い込んだら尋常でない集中力を発揮し、徹底的に突き進む性格によるところが大きい。浮川は、男性が一般的にそうであるように、あれこれ先のことを考え、周り見回して、計算ずくで動こうとする。初子は、できる範囲で、とりあえず段取りをつけて、突き進む。加えて、女性的なきめの細かさ、優しさがある。それが、すぐれたソフトウェアを開発できた要因になっている。
初子の突進力は、浮川さえも圧倒するというが、2人が互いに補完し合えば、非常に強力になるのは、容易に想像できる。
受注第1号は1,000万円足らずの仕事だったが、これをきっかけに、ジャストシステムの技術力は地元で知られるようになった。また漢字処理システムが、いっそう身近になったのも大きな収穫だった。
オフコンの事業は、この後も細々としたものだった。昼間、初子がコーディングしたものを、浮川が夜、パンチを打って仕上げる日々だった。一太郎を出すまでの6年間で売れたのは結局、1,000万円のオフコンを5セットと、パソコン数台足らずという。「売れないがために、コンピュータ化の提案書をたくさん書くなどして、この時期は経営の勉強にもなった」
オフコン上で1度だけ、ワープロをつくったことがあった。「文章をつくりたいからと頼まれて、簡単に文章をつくるような、変なワープロを作成したんですよ」
オフコンが売れないから、初子はこうした経験を積めたのかもしれない。
翌80年、徳島駅近くに事務所を構えた。14坪の賃貸オフィスだった。朝、2人で出勤し、お互いに向かい合って「おはようございます」と頭を下げて、仕事を始めた。81年には、社員6人の株式会社になった。相変わらず、注文は少なかったが、浮川には将来の展望が見えてきた。

1980年に移転した賃貸ビル
日本語処理の将来性に対する確信は、ますます強まり、日本語処理ソフトの開発に没頭するようになった。プリンタに漢字システムを組み込んでみたり、コンピュータ上での処理を考えてみたりと、日本語のことが常に頭にあった。
当時、マイコンと呼ばれた個人ユースの8ビット型コンピュータが世間に広まり始めていた。いまでいうパソコンだが、浮川はマイコンを買ってみて、意外に高性能なのに驚いた。そして、マイコン用の汎用ソフトのことを考えるようになった。「浮川が最初にパソコンを見たとき、これからは日本語変換システムだと思ったんです。コンピュータに関わりながら、彼がずっと思ってきたのは、そういう誰でも使えるものとしてのイメージ。そして、日本人が利用する際の一番根幹のところをやりたいと考えていたんです」と初子。
浮川はそうした思想をもちながら、ビジネス面でもパッケージソフト(店頭で売られる汎用のソフトウェア)を売る方が魅力があると思った。
1,000万円もするオフコンは、そう売れるものではないし、一度売れたら、技術者はシステムが完成するまで、顧客企業にかかりっきりにならなくていけない。土、日曜日でも呼び出される。パソコン用のパッケージソフトは単価は安いが、自由につくって、たくさん売ることができる。
といっても80年当時は、パソコン用パッケージソフトの市場が生まれて間もない頃で、まともな商品はほとんどなかった。ゲームソフトを中心に、カセットテープと、コピーした手書きのマニュアルをビニール袋に詰めたようなものが、秋葉原などの量販店の片隅に置かれていた。業界と呼べるほどのものはなく、一部マニアの市場だった。
浮川はこういう時期に将来を見ていたが、実際に飛び出すまでには、もう少し時間がかかる。
