つながる・広がる 地域と学校
メルマガで広がる「じぶん化」の輪
東京都・台東区立上野小学校 /教頭 佐久間茂和 先生 (取材時)
「学校メールマガジン」をはじめたわけ

―本日はお忙しい中ありがとうございます。
早速ですが、先生が発行しておられる学校メールマガジン(以下・メルマガ)についてお聞かせいただけますか?
佐久間先生(佐):
はい。私がメルマガ配信を始めたのは、前任校(台東区立台東小)でのことです。
きっかけは、子どもたちのお父さんに、もっと子どもと話してほしいと思ったことでした。お勤めのお父さんですと、どうしても子育てがお母さん任せになりがちで、子どもと話そうにも話題すらないということがよくあります。ですから、このメルマガで、今日の学校での出来事を知ってもらえれば、それを話題にした父子の会話が増えるのではないかと期待したのです。
―なるほど。最近では携帯電話でメールをお使いになる方も多いですし、職場でも読んでいただけますものね。
佐:そうです。実際、携帯電話で読んでくださっている方は相当の割合だと思いますよ。
メルマガが携帯で受信できる文字数を超えてしまうと、苦情をいただくくらいですから(笑)。
―どの程度のご家庭で読まれているのでしょうか?
佐:本校は、全校児童が435名、家庭の数で言うと340ほどになります。メルマガの配信数は300ほどですが、両親の分などを考えると、約半数以上の家庭で読まれていることになりますね。
この数には、子どもたちの家庭だけでなく、田舎の親戚や、卒業生の家庭などもいくらか含まれていますが、それでも、多くの方が学校での出来事に関心を持ってくださるようになったことは間違いありません。
メルマガ発行上の苦難
―その発行について、これまで何かご苦労はありましたか?
佐:まずはこれを「誰がやるか」が問題でした。
情報教育に付きまとう問題ですが、元々なかったことを始めるわけですから、先生方にも「余計な仕事」と受け止められがちで、なぜ仕事を増やすのか、という反応もありましたね。
ですから、最初は私のように、そうした作業が苦にならず、また、その効果について確信を持った人間が始めるしかないのです。そして、成果を積み上げることで理解を広めていきました。
実際に始めてみれば、たくさんの保護者の方や地域の方から、励ましや反響がありますから、そこで初めて「あ、こういう効果のあるものなんだ」「やるべきことなんだ」という意識を先生方に持ってもらうことができるんです。
前任校では、私が転任した後も、担当の先生がしっかりと発行を続けてくれています。今の学校でも、間もなく担当の先生に引き継ぐ予定です。
―先生という職業に限らず、新しい仕事に取り組むにあたっては、その仕事が何の役に立つのかを実際に示すことが一番のモチベーションになるという好例ですね。引き継ぎにあたっては、何かマニュアルをお作りになったのですか?
佐:私は研修などの際、メモを禁じているんです。体で覚えてほしいので、マニュアルも存在しないんですが、読んいただいている先生方のために、特別にポイントをまとめておきましょう。
佐久間流「学校メールマガジン」発行・運営のポイント
1.無料メーリングリストサービスなどは使わない
……広告挿入や名簿流出の危険あり
2.ウイルスに狙われにくいメールソフトを使う
……Windows標準のメールソフトは、ウイルス作者の標的になりやすい
3.宛先は自分自身(学校のアドレス)にして、購読者のアドレスはBCC欄に記入する
……各講読者に、他の講読者のメールアドレスが見えないようにするため
4.アドレス帳には、子どもの学年(一番下の子)と名前を入力しておく
……項目5の対応のため
5.卒業生には、継続して購読するかを確認して、アドレスを整理する
―ありがとうございます。その他には、何かエピソードなどありますか?
佐:本校がある台東区には、昔からの下町住人である方たちと、マンションなどに越していらした新しい住民の方、そしてさらに、外国から日本にいらした方も少なからず暮らしています。

そんな中で始めたメルマガなんですが、あるとき「読めないのでもうやめたいです」と仰るお母さんがいらしたんです。お話を伺ってみると、韓国からおいでになった方で、日本語は話せるけれど、読むのはやはり難しい。メルマガが送られてきても、なかなか内容が理解できないというのですね。
私は少しばかり語学をたしなんでいましたので、それなら、ということで韓国語のメルマガを発行することにしました。私の素人訳ですから、まさに片言だと思うのですが、頑張って続けています。本当は中国語など他の言語でも発行していきたいのですが、今のところはこれで精一杯です。ただ、ホームページの学校紹介だけは、英語、中国語(簡体/繁体)、韓国語でも制作しています。
地域=「五感・足のエリア」
―学校メールマガジンは、保護者や家庭に向けて発信されていると同時に、広く「地域」に向けたメディアでもあると思います。先生は「地域」というものをどのように認識しておいでですか?
佐:学校で「地域」というと、まずは学区の町会などに代表される町の人という印象を持ちますよね。あるいは、保護者を含めた三者、子どもたちを加えた四者の枠組みを想定することも多いでしょう。しかし、インターネットが普及した現在では、この「地域」がより大きな広がりを持つ可能性があると思っています。
―と、いいますと?
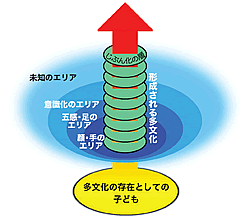
佐:例えば、メルマガを読んでくださっているのは保護者だけではないんですよ。田舎に住んでいる、子どもたちのおじいちゃんやおばあちゃんも愛読者だったりするのです。また、学校のホームページを見た卒業生が連絡をくれて、いろいろな分野で協力を申し出てくれる、ということもあります。このように地理的にも、あるいは時系列的にも広がりをもった、新しい「地域」というものの可能性が見えてくるように思うのです。
―なるほど。子どもという接点が距離を超えさせたり、また、学校の連続性が時間を超えさせたり、という広がりを生むことができるんですね。
佐:そうです。とは言っても、それでは「地域」というものがあいまいになりすぎるきらいもありますから、私は、こう考えてみました。「五感や足」が届く文化的な範囲が「地域」だ、と。
もちろん、ITや交通手段などの助けで、この範囲はさまざまに広がるわけですが、子どもを中心に広がるこうした範囲を、意識的に感じ取り、また感じ取らせることが地域を知り、活かすことだと思います。そしてそのことを「じぶん化(自文化・地文化)」と名付けています。
価値ある発信=「ローカル」であること
佐:私自身、教育の現場でインターネットの活用について考え始めた頃には「全世界に向けた情報発信」などと思案したものです。けれど、実際に取り組んでみて、そうではないことに気付きました。
自分がインターネットを使う身になって考えてみれば分かるのですが、欲しい情報とは、その発信者でなければ発信できない情報なのです。もっと言うと、その発信者が他の誰よりも知っていること、それを教えて欲しいんですね。つまり、自分の身近の出来事、身近にあることをしっかりと発信しているローカルな情報が、求められるし、信頼もされるんです。
―その「身近」とは、単に近くというだけでない「地域」のように広がりを持ったものだと考えていいのですね?
佐:その通りです。「五感・足のエリア」を基本に、「じぶん化」によって、そのエリアを深めたり、広げたりすることができるわけですね。
本校のホームページは、メルマガの内容と連動して、それに画像などを添えた「上野小トゥデイ」というコーナーを中心に、週2〜3回のペースで更新されています。この、ローカルに徹しつつも活気ある情報発信が、子どもたちばかりでなく、地域の人たちの「じぶん化」を進めていくきっかけになればと願っています。
 ◆台東区立上野小学校
◆台東区立上野小学校
インテリジェントスクールの理念に基づいて創設され、地域の生涯学習を支える社会教育会館と一体の施設として建設されている。学級と廊下の間に壁を持たないという構造もユニークだ。開校当初からコンピュータを取り入れた指導を行っており、情報モラルの教育にも力を入れている。児童数416名。
