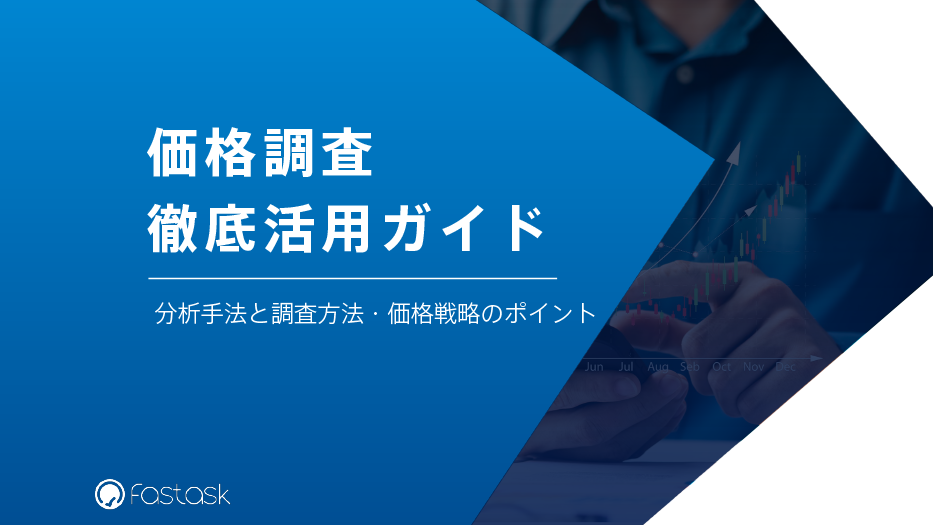市場調査とは?
種類・手法・やり方や流れをわかりやすく解説
—事例とAI活用も紹介

市場調査は、顧客ニーズや競合状況を把握し、戦略的な意思決定を支える重要なプロセスです。本記事では、市場調査の定義やマーケティングリサーチとの違い、定量・定性・デスクリサーチなど主要な手法の使い分けや調査の進め方、生成AIの活用可能性とその限界までを幅広く解説します。
また、セルフ型ネットリサーチツールであるFastaskを活用した具体的な調査事例も紹介し、実務での応用イメージが深まる構成になっています。調査初心者から実務担当者まで、あらゆるビジネスパーソンに役立つ内容です。
市場調査とは?
市場調査とは、企業が商品やサービスを展開する際に、顧客や市場の状況を客観的に把握するために行う情報収集活動です。消費者の購買行動やニーズ、競合の動向、業界の変化などを明らかにすることで、より的確なマーケティング戦略の立案や商品企画が可能になります。
①市場調査と
マーケティングリサーチの違い
「市場調査」と「マーケティングリサーチ」は、どちらも情報を集めることを目的としていますが、調査の対象や方法にやや違いがあります。市場調査は、市場全体の規模や動きや競合他社の存在、消費者の購買傾向など、主に「外部環境」を把握することに重点を置いています。一方で、マーケティングリサーチは、自社の商品やサービスについての印象や課題を調べ、より効果的な戦略を立てるための意思決定に役立てることが目的です。
②市場調査のメリット
市場調査の最大の利点は、マーケティング施策や経営判断に客観的な根拠を持たせられる点です。感覚や経験だけでなく、顧客ニーズや競合動向、商品コンセプトの受容性などをデータで明確にできます。これにより、戦略の精度が高まり、実行段階でのリスクも軽減されるでしょう。
さらに、消費者視点で意思決定を行う姿勢が社内に浸透すれば、商品開発やサービス設計の質も向上するでしょう。市場調査は、ブランド力や顧客満足度を支える基盤とも言えます。PDCAを回す際にも、信頼性の高いデータを活用することで、意思決定のスピードと確度を両立できます。
市場調査の種類や手法
市場調査にはさまざまな手法があり、調査目的や予算、スピードなどに応じて最適な方法を選ぶ必要があります。主な手法には、対象者の意識や感情の深層に迫る「定性調査」、統計的な分析で傾向や相関を探る「定量調査」、既存データを活用する「デスクリサーチ」、現場で行う「現地調査」などがあります。調査を成功させるには、手法の選定が調査目的と一致していることが重要です。
本章では、これらの代表的な市場調査手法を体系的に解説し、それぞれの特長と使いどころを明らかにします。以下は主な調査手法の一覧です。
| 調査手法 | 特徴 | 主な 活用場面 |
|---|---|---|
| 定性調査 | 深層心理や価値観を把握 | 商品開発、インサイト探索 |
| 定量調査 | 数字で傾向や相関を可視化 | 仮説検証、市場規模推定 |
| デスク リサーチ |
既存データや公的統計の活用 | 業界分析、予備調査 |
| 現地調査 | 実地観察やヒアリングによる調査 | 店舗改善、消費者行動の把握 |
① 定性調査
定性調査とは、個別インタビューやグループインタビューを通じて、対象者の意識や行動の背後にある理由や価値観を探る方法です。この調査では、回答者の言葉や態度を丁寧に読み取ることで、表面には現れにくい潜在的なニーズやインサイト(隠れた気づき)を見つけることができます。数字だけではわからない「なぜその行動をとったのか」という背景を明らかにできるため、新商品開発やコンセプトの検証など、企画の初期段階でよく使われています。
一方で、定性調査はサンプル数が少ないため、統計的な裏付けには適していません。しかし、仮説を立てたり、その仮説を深く掘り下げたりする場面では大きな力を発揮します。また、調査結果を正しく理解するには一定の分析スキルが必要なため、実施する体制をしっかり整えることも大切です。
② 定量調査
定量調査は、アンケートやWeb調査などを通じて多くのデータを集め、統計的な手法で分析する方法です。仮説の検証や市場規模の推定、属性ごとの違いの明確化など、論理的で再現性のある分析結果が得られます。結果が数値で表現されるため、社内の報告資料や意思決定資料としても使いやすいのが特長です。
大規模な対象者に短期間で調査できる点も利点ですが、設問設計を誤ると正確なデータが得られないリスクもあります。設問の構成や回答形式、選択肢の妥当性など、調査の信頼性を保つための配慮が欠かせません。
③デスクリサーチ
デスクリサーチ(Desk Research)は、既存の情報や公的資料を使って市場を把握する調査手法です。新たにアンケートを実施せず、官公庁の統計や業界団体の調査報告・企業のIR資料やニュース・過去の調査結果などを活用して、市場規模や動向、競合状況を把握します。予算や時間が限られている場面や、事前の仮説構築に有効です。
一方で、情報の鮮度や出典の信頼性、対象の一致性には注意が必要です。過去のデータに頼りすぎると、現在の市場を見誤るおそれがあります。そのため、目的に合った資料を選び、必要に応じて他の調査手法と組み合わせて活用することが大切です。
④現地調査、その他
現地調査(フィールドワーク)は、調査員が現場に足を運び、対象者の行動や周囲の環境を観察したり、直接ヒアリングしたりする手法です。たとえば、店舗での買い物行動や動線の観察、街頭でのインタビューなどが該当します。現場でしか得られない“生の情報”を収集できる点が強みであり、定量・定性調査だけでは得られないリアリティを補完します。
また、電話調査や郵送調査、FAX調査なども一部で活用されており、高齢者層やインターネットを利用しない層へのアプローチに有効です。調査対象や目的に応じて複数の手法を組み合わせることで、より精度の高い調査設計が可能になります。
市場調査の具体的な流れとポイント
市場調査は、単にデータを集めるだけでなく、その後の意思決定や施策に活かすために、一連のプロセスを体系的に設計・実行する必要があります。本章では、調査開始から結果の活用までの流れと、それぞれのステップでの注意点を解説します。調査設計の不備や目的とのずれが、調査全体の効果を大きく損なうこともあるため、各段階でのチェックが重要です。
①市場調査の流れ
市場調査は6つのステップで構成されており、それぞれの段階で明確な目的と判断が必要です。以下のフローは、調査を効率的かつ効果的に進めるための基本的な流れです。
| ステップ | 内容の概要 |
|---|---|
| 1 目的の 明確化 |
調査の背景と「何を知りたいのか」を明確にする |
| 2 仮説の設定 | 得られる可能性のある回答を事前に仮定する(例:若年層は機能性を重視している等) |
| 3 対象と設計 | 調査対象者の条件設定と調査手法の選定(定量・定性など) |
| 4 調査の実施 | 実査の実行(アンケート配信、インタビュー実施など) |
| 5 集計と分析 | 回収データの統計処理、傾向分析、仮説の検証 |
| 6 結果の活用 | 分析結果をもとに施策を立案し、現場に反映させる |
各ステップで最も重要なのは「目的と手法の一貫性」です。たとえば、目的が曖昧なまま調査を始めてしまうと、設問や対象の選定がぶれてしまい、結果が現場に活かせないケースが多くなります。調査の設計と実行を分けて考えるのではなく、常に全体像を意識しながら設計することが大切です。特に、結果を誰がどのように使うかを事前に決めておくことで、データの活用度が向上します。
②市場調査を成功させるためのポイント
市場調査において設計は重要です。仮説が具体的であればあるほど、設問や対象者の選定も精度が高まり、集めるデータの質が向上します。また、調査結果をどのような意思決定に使うのか、誰が見るのかまで想定しておくと、設計の方向性が定めやすいでしょう。
加えて、サンプル数や属性バランスも成功の鍵を握ります。たとえば「全世代の傾向を把握したい」のに20代の回答が偏っていた場合、分析結果に歪みが生じるからです。
③よくある失敗とその回避策
市場調査では、設計や実施の段階で生じた小さなミスが、大きな失敗に直結するケースがあります。たとえば、調査の目的が曖昧なまま始めてしまい、収集したデータが活用しづらくなるものなどが典型例です。また、設問が長すぎたり難解だったりすると、回答率の低下を招く恐れもあります。加えて、調査対象に偏りがあると、結果にバイアスがかかる可能性も高まるでしょう。
こうした失敗を未然に防ぐには、事前のレビュー体制が欠かせません。設問が目的に合っているかを第三者の視点で確認することで、論理の飛躍や曖昧な表現を排除できます。さらに、パイロット調査(テスト調査)を事前に実施することで、回収率や設問の理解度を検証し、改善のヒントが得られます。
また、「分析可能なデータ形式で収集されているか」「自由記述に偏りすぎていないか」といった点にも注意を払いましょう。調査は実施すること自体が目的ではなく、得られたデータを有効に活用するところまで設計してはじめて、成功したと言えるのです。
セルフ型のネットリサーチで市場調査

従来の市場調査は、専門のリサーチ会社に依頼するのが一般的でしたが、近年は「セルフ型リサーチツール」の登場により、社内で手軽に調査を行える環境が整ってきました。Fastaskのようなサービスを使えば、設問作成から配信・回収・分析までをすべて自社で完結できるため、時間とコストを大幅に削減できるでしょう。
①セルフ型定量調査
セルフ型の定量調査は、調査の立案から配信、集計・分析までをオンラインツール上で完結できる方式です。Fastaskのようなツールを使えば、専門知識がなくてもドラッグ&ドロップで設問を作成でき、Web上で対象者に自動配信され、結果はリアルタイムでグラフ化されます。数日で1,000件以上の回答が得られることも珍しくなく、スピード重視のプロジェクトに非常に有効です。
これにより、より細かな仮説検証や属性比較も容易になり、データドリブンなマーケティングの実践が可能です。結果をすぐに共有できるため、社内の意思決定プロセスにもスピード感が生まれます。
②セルフ型ネットリサーチを
活用するメリットとは
セルフ型ネットリサーチを導入する最大のメリットは、リサーチ業務の内製化による「高速かつ低コスト」の意思決定が実現できることです。従来の外注型リサーチでは、企画や見積、調整に時間がかかり、実査までに数週間以上かかることもありました。一方、セルフ型なら、準備から調査完了までを数日〜1週間で終えられ、マーケティング部門の機動力が大きく向上します。
回答者の属性や条件を指定したスクリーニング調査ができるツールも多く、BtoBからBtoCや主婦層から若年層まで、ターゲットに応じたきめ細かい調査設計ができます。専門人材に頼らずとも、一定のリサーチ品質を保てる点も大きな強みです。
③セルフ型ネットリサーチで
可能になる戦略や施策
セルフ型ネットリサーチは、単なるアンケートツールではなく、戦略策定から施策検証までを支える「実行可能な調査基盤」として活用できます。たとえば、広告出稿前後の認知度変化の追跡や、パッケージデザインの比較評価、WebサイトのUI/UX改善に向けたユーザー行動の定量分析など多様な用途に対応可能です。
マーケティング以外でも、新卒採用広報の反応評価や人事制度に対する従業員の満足度調査、CSR活動への意識調査など、部門横断での活用が進んでいます。調査結果はCSVやレポート形式で出力できるため、上層部への報告資料としても使いやすく、組織全体のPDCAサイクルを加速させる装置として機能します。目的を絞ったピンポイントな設計ができる点も、セルフ型ならではの魅力です。
生成AIで可能な市場調査とその限界
生成AIの進化により、これまで専門家やリサーチ会社が担っていた一部の調査プロセスが、AIによって迅速に代替できるようになってきました。ChatGPTやGemini、Claudeといった生成AIを使えば、過去の調査データや顧客インサイトの仮説を自動生成したり、インタビューの要約や質問案の提案を行ったりすることが可能です。初期段階の情報整理や仮説設計、アイデア出しといった領域で、大幅な業務効率化が期待されています。
①生成AIでできること
生成AIが得意とするのは、膨大な情報からパターンや傾向を抽出し、自然言語で整理してくれる点にあります。たとえば、競合他社のWebサイトやニュース記事から特徴や戦略の傾向を読み取り、リスト化するような作業には適しています。また、質問項目の候補出しやブレスト支援、インタビューの文字起こしを分類・要約するといった業務も、AIの活用によって効率的に進められるでしょう。複数の視点を短時間で提示できるため、仮説の比較検討が必要なフェーズでは特に有用です。
②生成AIの限界とリスク
一方で、生成AIには限界もあります。とくに「自社固有の課題に対して、実在する生活者の声をもとに精度の高いデータを取得する」「属性に基づく傾向や割合を定量的に把握する」といった用途では、AIだけでは不十分です。生成される内容は、過去に学習した知識や情報の推論に基づいており、現実の数値や人々の意見とは異なるケースも少なくありません。あくまで仮説構築や前工程の支援に特化したツールであり、精緻なデータ収集や仮説検証には、セルフ型のネットリサーチなど実証的な手法を組み合わせることが欠かせません。生成AIと専門ツールの適切な使い分けが、今後のリサーチ戦略を左右する重要な視点となるでしょう。
調査事例
—具体的な市場調査の活用例
セルフ型リサーチツール「Fastask」を活用した2つの実際の自主調査事例を紹介します。
①公式アプリに関する調査事例
マーケティングリサーチ情報サイト「Marketing Research Camp」ではネットリサーチサービス「Fastask」を活用し、「飲食店や小売店の公式アプリと消費行動の関係性」についての自主調査結果を公表しました。
調査によると、公式アプリを利用したユーザーのうち約3人に1人(34.6%)が、「店舗に来店したり、商品を購入したりする頻度が増えた」と回答しています。「その企業やブランドの情報を積極的に見るようになった」(21.7%)、「その企業の商品を周囲にすすめることが増えた」(15.7%)、「その企業やブランドの情報をSNSで拡散することが増えた」(15.4%)という結果がでました。
この結果により、企業情報への関心や周囲への商品紹介、SNSでの情報拡散といった行動も一定の割合で見られ、公式アプリが消費行動の活性化やブランド認知の向上に寄与していることが示されました。

②EC利用実態に関する調査事例
ネットリサーチサービス「Fastask」を利用して 『Eコマース&アプリコマース月次定点調査 (2019年1月度)』 の結果を発表しました。EC利用経験者のうち、海外のECサイトを「利用したことがある」人の割合は年代別で10代(57.1%)、20代(43.3%)、30代(30.8%)、40代(25.9%)、50代(23.9%)、60代(21.1%)となりました。すでに10代の半数以上は海外ECから商品を購入していることがわかります。
その結果、女性は「Instagram」、男性は「ネット記事」で、「海外ECサイト」を知るきっかけとなっていたことがわかりました。また、海外ECを利用する理由は「日本にない商品がある」、海外ECのトラブルは「配送遅延」と答えた人が3割以上もいました。

まとめ
本記事では、市場調査の基本的な定義から代表的な手法、調査の流れ、生成AIの活用、そして実際の活用事例までを網羅的に解説しました。市場調査は単なる情報収集ではなく、マーケティング施策や商品開発、ブランド戦略など、あらゆる経営判断に直結する「意思決定の根拠」を提供する重要な活動です。
とくに、仮説検証やユーザー理解といったピンポイントな課題に対しては、Fastaskのようなセルフ型リサーチツールが有効です。社内の調査力を高めることで、外部委託に頼らずともスピーディかつ柔軟な意思決定が可能になります。目的に応じた手法とツールを選び、精度の高い情報に基づいたアクションを実現してください。
セルフ型ネットリサーチツールを検討している方は「Fastask」にお気軽にご相談ください。また参考資料もご用意していますので、ぜひ以下のリンクからご活用ください。
マーケティングリサーチ実践ガイド
マーケティングリサーチを成功させるために必要な統計知識をはじめ、サンプルサイズの決め方や調査実施・集計分析の方法などをわかりやすく解説します。
Fastask(ファストアスク)とは?
ジャストシステムが提供するセルフ型ネットリサーチサービス。調査する企業が自分で質問を作成するスタイルで、ローコスト&スピーディーな調査が可能です。従来調査の半額~10分の1の費用で、即日~数日で調査が完了します。
Sprint(スプリント)とは?
ジャストシステムが2017年8月にリリースした、「わずか5分でターゲットとなる消費者に出会えるチャットインタビューサービス」で、インターネット上で定性調査のインタビューができます。従来のリアル・インタビューよりもはるかにスピーディーで低コスト、リアルタイム性があるのが大きな特徴です。話を聞いてみたい人を選んで手軽にインタビューできます。
 HOME
HOME